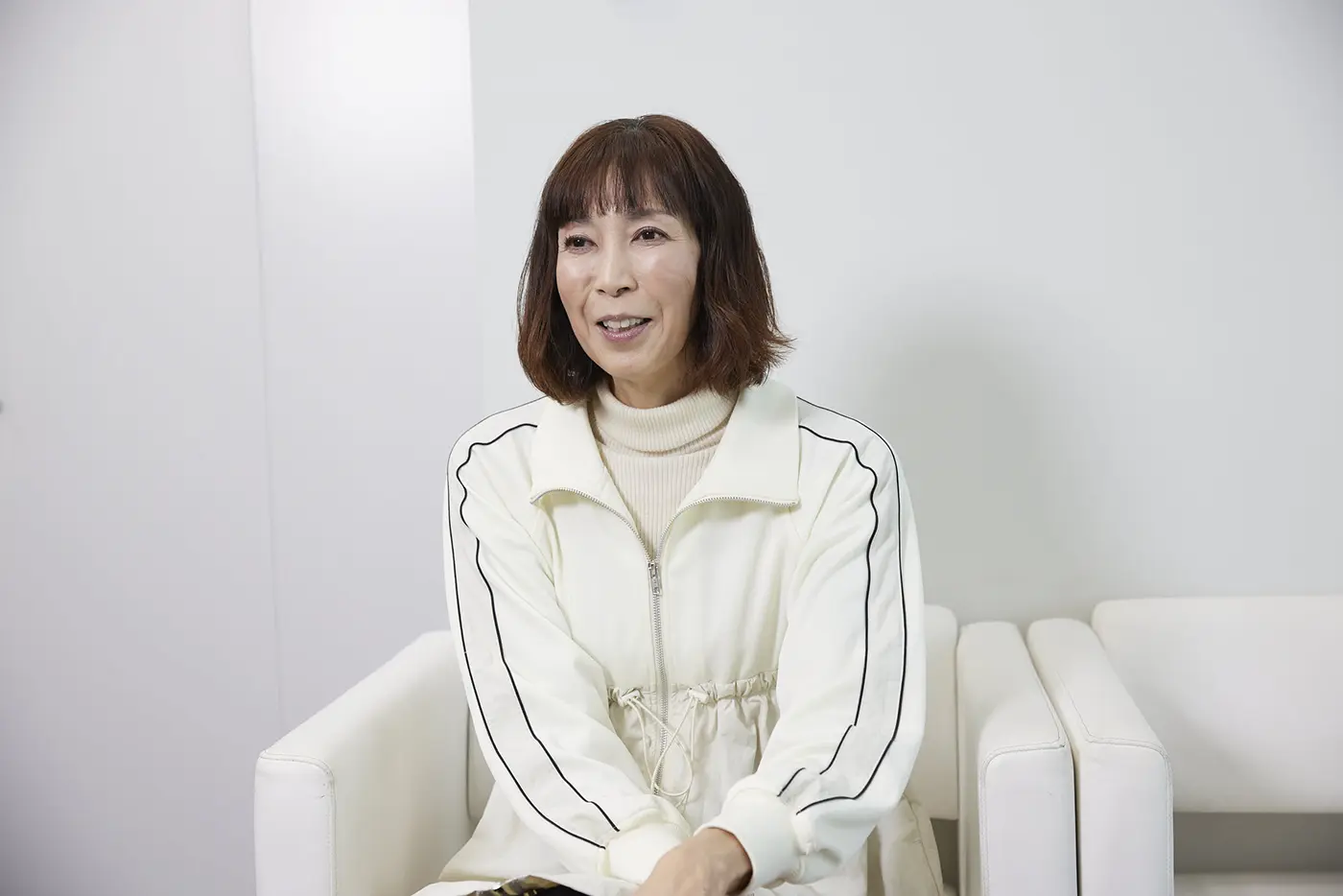パラスポーツに関わる方々に、出会いのきっかけや今後への想いをお聞きしました。
パラスポーツとの距離を感じた現役時代
私が現役だった1990年代までは、オリンピックスポーツとパラスポーツの接点はほとんどありませんでした。今でこそ、テレビやイベントで選手同士が交流する機会は増え、ナショナルトレーニングセンターで練習、合宿を一緒にできる環境も少し整ってきました。しかし、1980年代は、そもそもナショナルトレーニングセンターもなかったので、オリンピアンが集まる環境もなかったし、オリンピック後にパラリンピックの開催となるから、なかなか接点もありませんでした。 ですから、パラスポーツといえば、テレビやニュースで見ること以外、交流もあまりなかったのが、 1990年代前半ですね。

私が引退したのは1997年、翌年に長野1998冬季オリンピック・パラリンピック競技大会を控えた年です。その後、東京にオリンピック・パラリンピックを…という機運が高まり、2013年9月に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催が決定しました。それをきっかけに、メディアでも積極的にパラアスリートが取り上げられるようになり、私もレポーターとして選手を訪ねたり、競技を体験させていただいたりと、パラスポーツに関わる機会が増えていきました。
そんな中、印象的な出会いがあったんです。
“気遣い”なんていらなかった
海外で義足のランナーに取材をさせていただいたときのことです。パラアスリートの方と接する機会がなかった私は、「自分が彼女をケアしなくては、できることをやらなくちゃ!」と意気込んでいたのですが、あたふたしている私の様子を見て逆に「大丈夫?」と気を遣われてしまいました…。彼女が私の想像よりも遥かに強いメンタルを持っていることに尊敬や感動に近い衝撃を受けるとともに、自分の先入観を恥じたというか、己を見つめ直す機会をいただいたような出来事でした。
パラアスリートの中には、ハンディキャップを抱える悔しさや、今までと同じ自分ではないという現実を乗り越え、それらと付き合っていく強さを持っている人が多いです。だからこそ、私たちは思いやりを持ち、普通に接することが大事だと思いました。
もちろん、車いすや松葉杖を使う上で不自由なことがないか気遣うことは必要ですが、それはお年寄りや、困っている人を気遣うのと同じこと。人として当たり前の思いやりです。「パラスポーツやパラアスリートとの接し方がわからない」という人は、まずは普段の心持ちで接してみてください。関わっていくうちに少しずつ垣根を感じなくなり、自分にできることがきっと見えてくると思います。
“パラスポーツって楽しい”を伝えたい
最近では、私が体験から感じたこと、身につけた感覚を誰かに伝える機会が増えてきています。一番交流があるのはパラバレーボールです。真野嘉久さん(一般社団法人日本パラバレーボール協会 前会長)にお声がけいただき、試合やイベントに参加させていただいたり、番組に出演したり。私がGMを務めていたブレス浜松(静岡・女子プロバレーボールクラブ)でも、パラバレーのエキシビションマッチや体験会を企画したこともありました。 『身近で観て、感じて、体験できる場所作り』に関してのかけ橋になるようなお手伝いは、私自身これからより一層、取り組んでいきたいと思っています。
パラバレーボールはシッティングバレーボールとも呼ばれますが、実はバレーボールとはまったく違う競技なんです。「大林さんは得意でしょ」ってよく言われるのですが、座った状態での移動が難しくてバレーボール経験者でもなかなか戦力になれません。
でも、座りながらボールに触れますし、走らなくていいので、障がいの有無にかかわらず子どもからお年寄りまで一緒に楽しめる。そういった競技の特長や純粋な楽しさが伝われば、もっともっと広められるんじゃないでしょうか。
ほかにも、アスリートがスポーツの力で社会課題の解決に取り組む「HEROs」の活動として、根木慎志さん(シドニー2000パラリンピック競技大会車いすバスケットボール日本代表主将)と一緒に車いすバスケットボールの体験会を開催しました。体験授業も、何度かご一緒させていただいています。

参加した子どもたちは初めて乗る車いすに興味津々で、車いすに座ったときの目線が普段と違うことが新鮮な発見のようでした。根木さんには「どうやって動かすの?」、「回転はどうするの?」などと質問の嵐。「私も乗りたい!」と順番待ちの列もすごかったですね。
彼らが今後、車いすを使用している人に対して何を感じ、思うのか? イベントを通して実際に車いすを操作する大変さを体感したことは、大きな学びの時間になったのではと思っています。このような機会も、これから増やしていきたいことの一つです。
私にはパラスポーツの魅力を伝える使命がある
スポーツ以外のお仕事では、テレビや講演、舞台への出演が多いのですが、『消せない約束』という映画で足の不自由な人の役をやらせていただいたこともありました。撮影中、車いすにとって不便な場所が街にはたくさんあって、まだまだバリアフリーは遅れているなと感じたり、根木さんのおかげで車いすに乗り慣れているから役作りがしやすいなって思ったり(笑)。
それは、わずかながらも私が不自由であることの大変さを知っていて、本当に少しですが、その方たちの目線で、見る意識ができるようになってきたこともあると思います。
道を歩いていても、障がいのある友人と食事に行っても、段差や通りづらいところがぱっと目につくようになりました。
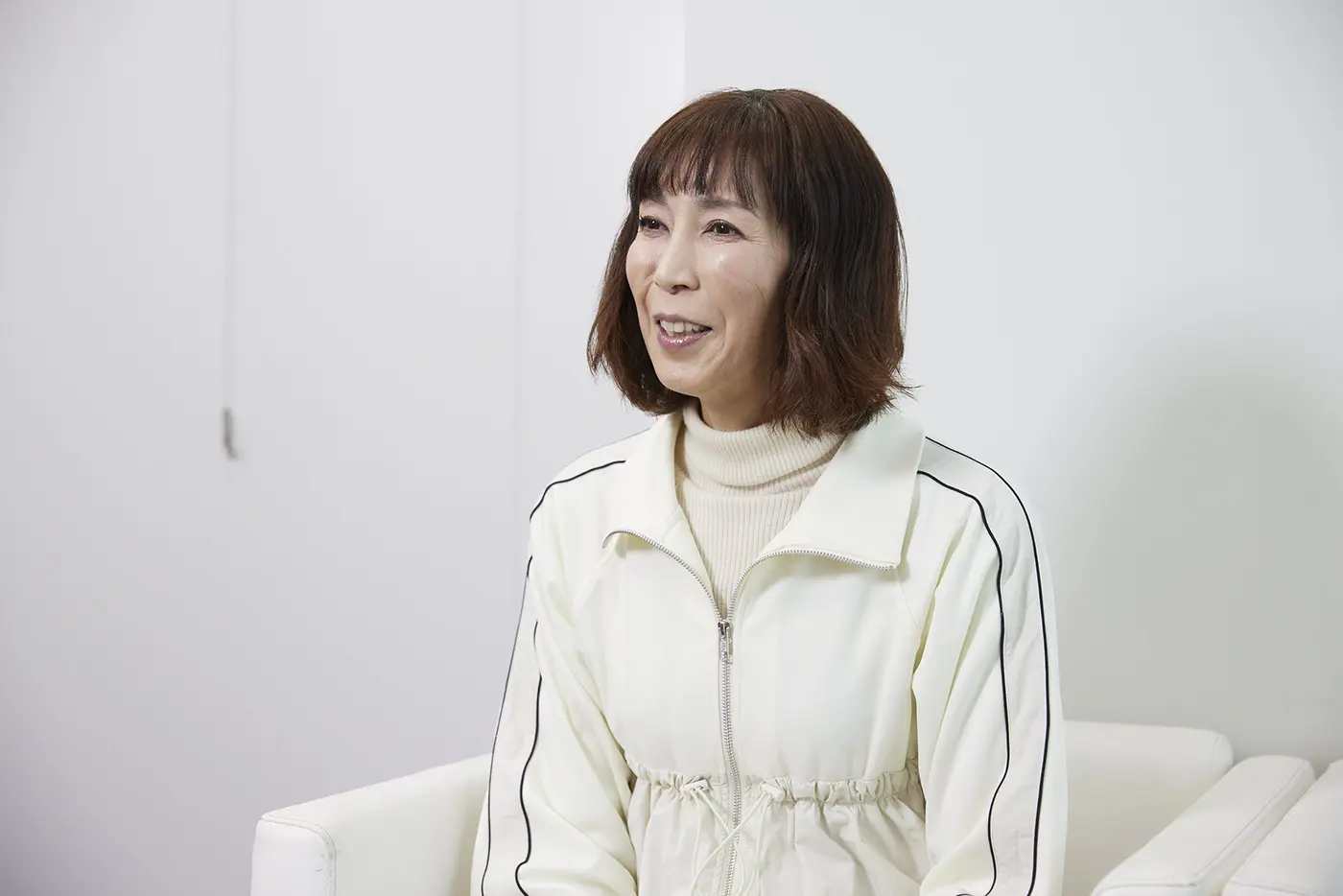
このように現在の私の生活やお仕事というのは、障がいを抱えた方たちやパラスポーツとつながっています。だからこそ、私には「つながることの大切さ」を世の中に伝える使命があるのかも、と勝手に気合いを入れています。今はまだボランティアに参加しているレベルですが、そろそろ腰を据えた大きな活動で貢献しなきゃいけないなと考えているところです。
全国のパラスポーツ活動が連動すれば、人も注目も集まるはず
これまでにいろいろな地方に足を運びましたが、パラスポーツの活動情報がもっと連携して発信されるといいなって思っています。というのも、各都道府県の活動は、個別に、単発的に行われていて、次はいつ開催されるのか、ほかの競技はどこでやっているのかといった情報がまとまっていないことが多いように思います。アクセスしやすいプラットフォームみたいなものがあると、調べるのが得意でない人も参加しやすいですよね。
そうすれば、パラアスリートもゲスト講師として呼びやすくなると思うんです。パラスポーツにはまだ敷居が高いイメージがあって、誰を、どこに招けばよいのか問い合わせる窓口が少ない。著名人や、アスリートを講師として派遣するサービスがありますが、そういう仕組みがパラスポーツにもできれば、人も注目も集まりやすくなるはずです。
スポーツ教育において、アスリートを使わないなんて宝の持ち腐れですよね。実際、講師をやりたい選手は多いのに、人の縁しか頼れないから、関わりの少ないパラスポーツ界には講師が呼ばれにくい現状があります。これからは日本代表レベルのパラアスリートたちがもっと教育に関われる機会を増やしていきたいですね。
パラスポーツがいろいろなメディアで取り上げられる時代になりましたが、まだまだ日常で触れる機会は少ないまま。今後はパラスポーツがママさんバレーやフットサルのように当たり前の存在になり、誰もがいつでも楽しめる地域に根付いたスポーツになっていったらいいなと願っています。